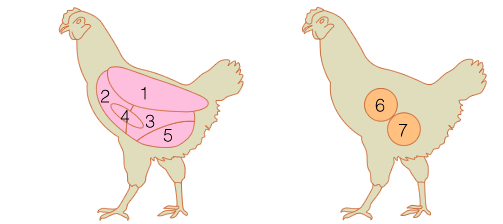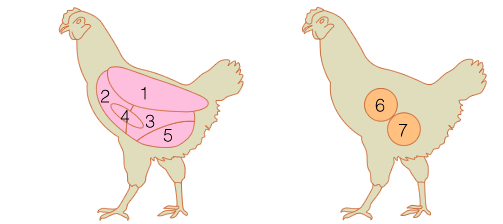| 【1】手羽類 |
手羽類は「手羽もと」「手羽さき」「手羽なか」に分けられる。「手羽もと」は上腕部分、「手羽さき」は上腕から手羽もとを除去した残りの部分、「手羽なか」は手羽さきから手指を除いた部分をいい、チューリップとしても売られている。手羽もとより手羽さきのほうが濃厚な味がする。肉は白くやわらかい。脂肪やゼラチン質に富み、味にこくがある。煮物や揚げ物にあう。 |
| 【2】むね肉 |
胸の部分肉。骨つきもあるが、骨を取り除いた胸の正肉だけのものが一般的である。肉質はやわらかく、脂肪が少ないので味は淡白。油の風味とよくあうので揚げ物などがおいしい。 |
| 【3】もも肉 |
脚からももの付け根の部分。骨なしが一般的。骨つきもも肉はレッグといい、下半分はドラムスティックという。肉質はむね肉よりかたく筋がある。脂肪が多く、味にこくがある。焼き物、煮物に向く。 |
| 【4】ささみ |
むね肉で手羽の内側にあり、形がササの葉に煮ている。牛・豚肉のヒレに相当する部分で肉質はやわらかく、白身の肉で最高の品質。脂肪が少なくて淡白。さっとゆでたり、新鮮なものは刺身でもよい。 |
| 【5】かわ |
脂肪が多くやわらかい。味は濃厚で、胴体のものより首皮のほうが味がある。皮の裏の脂肪をとって湯通ししてから、炒め物、煮物、和え物などに利用する。鶏肉の他の部分に比べて価格は安い。 |
| 【6】きも(肝臓) |
肝臓はきめが細かく、くせがないので食べやすい。心臓部分は、心筋で構成されているので独特の歯ざわりがある。周りの脂肪をとり、血抜きをして使う。焼鳥、もつ焼きが一般的だが、煮物、揚げ物、炒め物にもおいしい。 |
| 【7】すなぎも |
胃袋の筋肉の部分でニワトリ独特の内蔵。「筋胃」「スナブクロ」「サノウ」ともいう。脂肪がほとんどなく、こりこりとかたい。臭みが気にならないので生食もできるが、もつ焼きが一般的。から揚げ、炒め物にも。筋周辺が青っぽいのが新鮮。 |
鶏は、鳥類のなかではキジ科ニワトリ属に分類されます。四千年以上昔に人間が野生の鶏類を飼い慣らして創り上げたものです。これら野生の鶏は、主に東南アジアに分布していて4種類います。赤色(せきしょく)野鶏、セイロン野鶏、灰色野鶏、緑襟(あおえり)野鶏で、その中の赤色野鶏が鶏の祖先だと考えられています。
さて、鶏を飼い始めた場所はアジアのある地方であることに間違いないのですが、それから鶏は変異を繰り返して今に至っています。その結果、産地は極地を除き世界各地に渡り、種類は240種以上あるといわれています。日本鶏の種類でいえば、地鶏群と呼ばれる種類の鶏の祖先だったと考えられています。その後、江戸時代初期まではめぼしい外国鶏の渡来もなく、(平安時代に中国から渡来した小国だけ)、仏教の影響から卵や肉を食べるという習慣もなかったため食用の養鶏は発展せず、また愛玩養鶏も発展していたとはいえず、鶏は雑種や変異種はいてもそれ以上の発展はなかったと考えられています。しかし、江戸時代に入ると徳川家康が朱印船貿易や外国貿易に力を入れはじめたため、中国、インドネシア、マレーなどから色々な鶏(シャモ、チャボ、烏骨鶏、唐丸など)が渡来してきました。その後鎖国が始まり外国産の新しい種類の渡来は困難になりました。江戸時代の泰平の世、色んな文化が興隆する中、鶏もまた愛玩用(ちゃぼ)や賭事用(闘鶏−しゃも・薩摩鶏)として飼われはじめました。そして数少ない鶏種の中から品種改良が進められ、現在の日本鶏の品種が創造されたといわれています。
明治の頃から、養鶏用に外国品種が輸入され始めました。小規模の農家養鶏が始まり、鶏そのものの性能研究が始まりました。 鶏の性能を求めて、主にアメリカで育種開発されたものが輸入されてきました。ロードアイランドレッド、横斑プリマスロック、ニューハンプシャー種などです。コーチンも輸入されて、名古屋コーチン、熊本コーチンの基礎鶏となりました。
同時に、地域に在来している鶏種の中から、産卵性能の適しているもの、肉用に向いているものと、食用に用いられる鶏種(比内鶏、岐阜鶏、薩摩鶏など)が出てきました。コーチンなどとの交配で名古屋コーチン、熊本コーチンが固定化されました。
産業用として養鶏事業が日本で成長し始めたのは、第二次世界大戦後の昭和36年頃からです。まず採卵養鶏が事業化されました。(アメリカ・カナダで育成された採卵専用種が輸入されて活発に成長しました)
これは鶏種としては、ホワイトレグホン種になります。 肉養鶏は昭和39年の東京オリンピックの頃からです。肉用も肉用専用種が輸入され始め、日本のブロイラーインテグレーターの興隆とともに活発になりました。現在の大手のインテグレーターの創始期もこの頃です。
鶏種は、ホワイトコーニッシュ(♂)、ホワイトプリスマロック(♀)です。
日本鶏の種類は本格的な標準草案を作成した故小穴彪氏の著作『日本鶏の歴史』の中で次の4群に分類されています。(尚、赤文字は天然記念物指定、その他、県指定の天然記念物指定も多数ある)
戦後、日本では若どり(ブロイラー)が広く普及してきましたが、さまざまな理由から「昔の鶏の味」と懐かしむ声が高まり、昭和50年代頃から地鶏が登場してきました。
しかし、地鶏が売れることがわかるとごく一般のブロイラーや老いた親鶏を地鶏と称して販売したり、地鶏であっても大量生産を図るため、飼育施設が若どりと同じものが出てきたりして、流通現場では混乱を生じてきました。
そこで平成7年(社)日本食鳥協会が品種や飼育方法、出荷日数を工夫した品種を「国産銘柄鶏」。さらにその中を「地鶏」と「銘柄鶏」に分けるガイドラインを打ち出しました。それによると「地鶏」とは古来より日本に在来していたといわれる品種、もしくは明治初期ごろまでに日本人が外来種と掛け合わせて作り出した鶏(日本鶏)のことをいいます。現在生産されている「地鶏」は種そのものの希少性(多くの日本鶏が天然記念物に指定されているためそのまま食べることはできない)や、生産コストの関係上、日本鶏の血統が50%以上入った交配種(F1)であればよく、ほとんどの「地鶏」がこの部類になります。それに対し、外国の鶏種や日本鶏の血統を使っていても50%以下のものは「銘柄鶏」と呼ばれます。